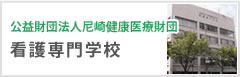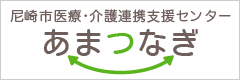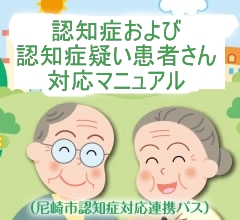「医政フォーラム並びに民間病院・公的病院と医師会との懇談会」(第666号 令和7年6月6日)
2025/07/01(火)
令和7年5月24日(土) 午後4時より
都ホテル尼崎 鳳凰の間にて
医政委員会委員 稲本 真也
令和7年5月24日16時から尼崎市医師会医政フォーラムが、都ホテル尼崎鳳凰の間において開催されました。今回は初の試みとして民間病院・公的病院と医師会との懇談会との同時開催となりました。生憎の雨天でしたが大勢の方が参加され、会は盛況のうちに始まりました。
総合司会は夏秋恵氏(尼崎市医師会理事)が務められ、まず杉原加壽子氏(尼崎市医師会会長)の挨拶で開会しました。次いでご来賓の八田昌樹氏(兵庫県医師会会長)、坂本泰三氏(日本医師会常任理事)、加田裕之氏(参議院議員)よりご挨拶をいただきました。話題は多岐に渡りましたが、医療が岐路に立っているという危機感がお三方の挨拶に滲み出ていたことが印象的でした。ここで自民党参議院議員の末松信介氏よりご祝辞をいただき、第一部の講演「今後の地域医療構想について」が開始となりました。座長の原秀憲氏(尼崎市医師会副会長)の進行で始まり、釜萢敏日本医師会副会長が登壇されました。せっかくの機会なので講演の内容を要約してお伝えします。
第一部:釜萢敏日本医師会副会長による講演「今後の地域医療構想について」
釜萢敏日本医師会副会長はまず我が国の人口変動と医療・介護のニーズの変化について、具体的なデータを用いて共有されました。総人口は減少しており、高齢者人口は増加の一途を辿る一方で若年者人口の減少と出生数の低迷(年間70万人割れ)は極めて危機的です。外来患者数は高齢者では減少傾向に転じており、地域差はあるものの病床利用率の低下が見られる一方で在宅医療が必要な患者数は増加が続いています。救急搬送される患者に占める65歳以上の割合は増加し、特に85歳以上の超高齢者の搬送が急増しています。以上のデータから地域医療が高齢化のニーズに対応していく必要性を強調されました。
前段でお話しされた内容を基に、2040年に向けた新たな地域医療構想について説明がありました。これまでの地域医療構想が病院では病棟単位での機能分化に焦点を当てていたのに対し、新たな構想は「すべての地域、すべての世代の患者が適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院し、また日常生活に戻ることができる」という、より包括的なビジョンを掲げています。特に強調されたのは介護分野との連携強化、また「治す医療」と「治し・支える医療」との役割分担です。この新たな構想を実現するための主要な検討課題として、以下の4点が挙げられました。
•高齢者救急への対応: 増加する高齢者の救急搬送に適切に対応できる地域医療提供体制の構築。
•在宅医療の推進: 増加する在宅医療の需要への対応と地域の実情に応じた柔軟な在宅医療の提供体制の確保。
•医療の質と人材確保: 医療従事者の持続可能な働き方を確保できる医療提供体制の確立と抜本的な処遇改善、医師の地域的な偏在と専門医の偏在の是正。
•地域医療提供体制の維持: 人口減少が加速する地域においても、必要な医療提供体制を維持するための具体的な方策。
これらを元に新たな地域医療構想での変更点として、地域医療構想の対象範囲を外来、在宅、介護連携などに拡大すること、病床機能について「回復期」を「包括期」へと見直し高齢者の急性期医療への対応機能を強化することが示されました。また日本医師会としては地域医療構想を「地域医療介護構想」への変革と調整会議の活性化を提案しています。
加えて釜萢敏日本医師会副会長は、かかりつけ医機能報告制度について背景と今後の見通しを述べられました。今年4月開始のかかりつけ医機能報告制度は医療費抑制を狙う財務省主導で進められようとしたものではあるが、本来「かかりつけ医」は患者が選ぶべきものであり、日本医師会は現状通りすべての医療機関がかかりつけ医機能を担いうるとの立場です。医療機関は研修参加などでかかりつけ医機能を発揮している実績を積むことが重要だと強調されました。
第二部:意見交換会
講演の後にコーヒーブレイクを挟んで意見交換会が行われました。事前に用意された病院からの質問に釜萢敏日本医師会副会長が回答する形で活発な議論が展開しました。
稲本(尼崎だいもつ病院)、城大介氏(尼崎新都心病院)、鷲田和夫氏(鷲田病院)、東一氏(尼崎医療生協病院)、橋本創氏(園田病院)、池内浩基氏(兵庫医科大学病院)の各先生方から質問があり、釜萢敏日本医師会副会長が回答、坂本常任理事が補足される形で議論が進みました。
質問内容は、高齢化社会に対応した医師の養成、病床削減の問題、パンデミックの際の病床不足の問題、病院機能のあり方の問題、医療従事者のメンタルサポート、地域の看護学校経営と看護師不足、特定機能病院と大学病院からの地域医療への指導医を含む医師派遣の難しさ、医師の働き方改革の影響と若手医師の意識の変化など非常に多岐に渡りましたが、釜萢敏日本医師会副会長からは各々について医師会が重大な問題意識を持って前向きに検討することが示されました。
特に時間を割いて議論されたのは、昨今の物価高騰や処遇改善による病院の負担増と診療報酬の問題です。承知のごとく現在の病院経営は医業利益での赤字病院が全体の7割に及ぶなど非常に厳しいものがあり、各病院からの質問内容は切実かつ悲痛なものですらありました。これに対して釜萢敏日本医師会副会長より、適正な収支差を確保できるような診療報酬への抜本的な改定が是非必要であること、医療・介護現場の厳しい現状を広く国民に伝え適正な報酬設定が「儲け」ではないことを理解してもらう必要があること、医療機関や介護施設が体力をつけるため適正な収支差が得られるよう全力で取り組んでいることを伝えていただきました。また病床削減についても減反補助金的な対応によって地域のsurge capacityの消失につながらないよう注視が必要と述べられました。残念ながら先生によると、病院の経営危機の問題は国会議員の間ではだいぶ理解が進んできたと感じられるものの、政府では理解が進んでいるとは言えないということです。これからも粘り強く政治に働きかけを続けていく考えを述べられました。坂本常任理事からは医療・福祉業界は自動車業界に匹敵する922万人(2024年平均)もの人材を擁しており、その力を結集して政府や関係各所に働きかけていく必要があるという呼びかけがなされました。
講演の終わりに八田兵庫県医師会会長がコロナ禍での尼崎市内の医療機関の連携について触れられ、医師会の意見要望を聞きながら地域の連携を進めていきたいとの考えを述べられました。そのあと八田会長ご自身が釜萢ブルーの鉢巻と上着を着用して音頭を取られ、「国民にとってより良い地域医療構想を目指し、良い診療報酬改定になるように」という想いを込めて頑張ろうコールを全員で唱和し、この日最大の盛り上がりとなりました。
最後に中川勝氏(尼崎市医師会副会長)が、医療現場の危機的な状況を釜萢敏日本医師会副会長に中央に伝えてもらいたい、それを達成するために医師会が全力をあげて釜萢敏日本医師会副会長を全力で応援する所存であると決意を述べられ医政フォーラムが終了しました。
短い時間ではありましたが、釜萢敏日本医師会副会長のご講演をはじめ濃密で有意義な情報交換ができたと思います。第二部のテーマは質疑応答の形を取りましたが「これからの日本と医療界の団結」というものでした。この日のフォーラムを通じて、我が国の医療を取り巻く厳しい現状と今後の指針が理解できたと思います。またそれを打破するための決意と医師会の団結の重要性を改めて感じることができました。貴重な機会を得ることができたことに、釜萢敏日本医師会副会長をはじめ関係の各先生方に深く感謝します。